|
|
|
|
 ひがし茶屋街(2012年6月4日) |
 ひがし茶屋街(2012年6月4日) |
 ひがし茶屋街(2012年6月4日) |
 ひがし茶屋街(久連波・友禅) |
 ひがし茶屋街 |
 ひがし茶屋街 |
 |
 |
 |
| ひがし茶屋街を散策の観光客 | ひがし茶屋街を散策の観光客 | くるみや(喫茶) |
. 金沢市東山・ひがし茶屋街(2011年4月6日) |
 金沢市東山・ひがし茶屋街(2011年4月6日) |
 金沢市指定保存建造物「懐華樓」 |
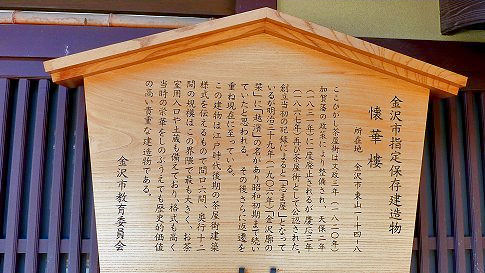 金沢市指定保存建造物「懐華樓」説明表示板 |
|
|
 金沢市東山・ひがし茶屋街(志摩・左側建造物) |
 国指定重要文化財「志摩」 |
 国指定重要文化財「志摩」 |
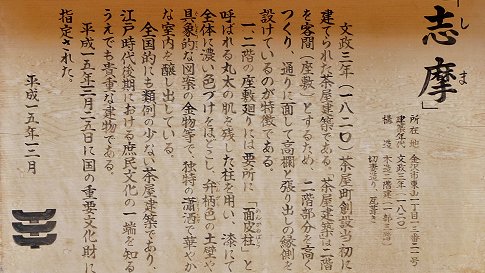 国指定重要文化財「志摩」説明板・平成15年12月25日 |
 |
 |
 |
| 典型的なお茶屋の庭 | 囲炉裏 | 台所 |
 |
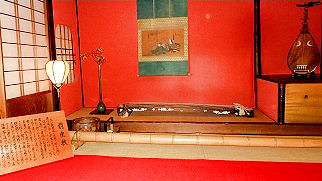 |
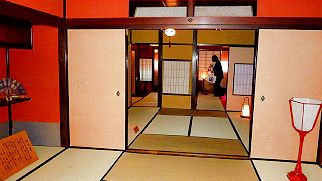 |
| ひろま | 前座敷 | ひろま・なかの間・前座敷 |
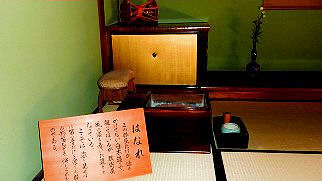 |
 |
 |
| はなれ | 寒村庵(抹茶も頂ける・有料) | 浅野川に架かる梅の橋 |
|
|
 主計町茶屋街 |
 主計町茶屋街 |
 正面見える浅野川大橋詰火の見櫓(国登録有形文化財) |
 浅野川大橋(国登録有形文化財・建造物) |
 浅野川大橋 |
 浅野川大橋(国登録有形文化財・建造物) |
 |
 |
 |
| 主計町茶屋街 | ひがし茶屋街側より主計町茶屋街望む | 大橋取付の国登録有形文化財版 |
| 浅野川大橋周辺の歴史ある建造物。 |
 |
 |
 |
| 歴史ある綿谷小作薬局(創業1667年) | ビストロとどろき亭(1921年建築) | 徳田秋聲記念館 |
撮影日時・2011年4月6日・2012年6月4日
![]()
メインページへ
![]()
資料
地元発行の観光パンプレット・HP及び施設説明表示板