|
|
|||
 最大洞杉・2004年の計測で幹周合計30.18m |
 洞杉観察道案内図 拡大 |
||
 魚津市道南又線沿いの「市道横洞杉」 |
 魚津市道南又線沿いの「市道横洞杉」奥の洞杉 |
||
 魚津市道南又線沿いの「市道横洞杉」 |
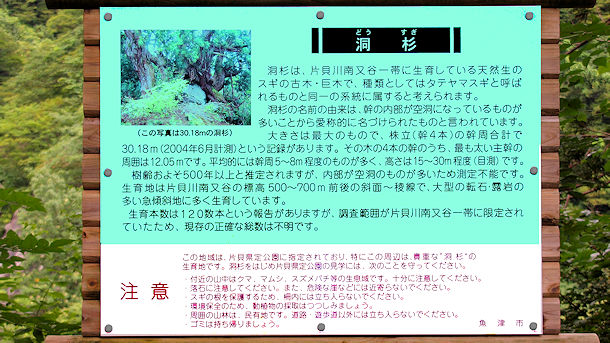 洞杉説明板 拡大 |
||
 南又谷川の龍石(蛇石) |
 蛇石から上流(巨石が多い) |
||
 成谷1号砂防ダム |
 下流より成谷1号砂防ダム |
||
 黒谷頭首工 |
 北陸電力片貝第三発電所 |
||
 東山円筒分水漕 国の登録有形文化財(農業用水利施設) |
 東山円筒分水漕 国の登録有形文化財(農業用水利施設) |
||
 蔵の下橋から布施川ダム湖 |
 蔵の下橋・布施川ダム湖 |
||
 市道横洞杉 |
 市道横洞杉幹廻り(←図左側) |
 市道横洞杉幹廻り(←←図右側) |
 新土倉橋 |
 新土倉橋より上流の砂防堰堤 |
 新土倉橋より下流 |
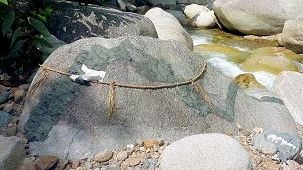 龍石 |
 龍石祠(りゅうせきのほこら) |
 蛇石橋 |
 小沢谷橋周辺の砂防堰堤 |
 南又谷川に架かる小沢谷橋 |
 小沢谷橋周辺の南又谷川 |
 砂防堰堤 |
 高木橋 |
 高木橋より上流の砂防堰堤 |
 成谷1号砂防ダム上流の砂防ダム |
 成谷1号砂防ダム |
 成谷1号砂防ダム銘板 |
 北陸電力片貝第四発電所 |
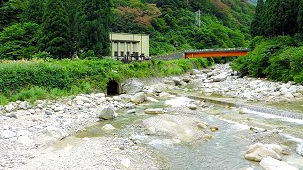 東又谷川と南又谷川合流地点 |
 北陸電力片貝第一発電所 |
 北陸電力片貝第二発電所 |
 周辺の片貝川 |
 小坂橋 |
 黒谷頭首工右岸から対岸を望む |
 黒谷頭首工 |
 黒谷頭首工 |
 黒谷橋(すぐ上流は黒谷頭首工) |
 黒谷橋より下流 |
 東山円筒分水漕(農業用水利施設) |
 東山円筒分水漕(農業用水利施設) |
 東山円筒分水漕説明板 拡大 |
 右岸から東山円筒分水漕前の片貝川 |
 東山橋より上流 |
 対岸のタワーパートナーズ工場 |
 片貝川に架かる東山橋 |
 東山橋下流 |
 片貝橋から対岸 |
 片貝橋 |
 片貝川に架かる落合橋 |
 落合橋より上流 |
 落合橋より下流 |
 富山地方鉄道片貝川・布施川橋梁 |
 魚津工業高校と立山連峰 |
 河口付近の布施川との合流地点 |
 河口より対岸・富山湾 |
 左岸河口より富山湾 |
 経田漁港 |
| 支流の布施川 | |||
 布施川ダム堰堤 |
 布施川ダム堰堤を望む |
 蔵の下橋 |
 蔵の下橋より上流 |
 蔵の下橋上流の砂防ダム |
 布施川ダムの放流路 |
 布施のみどり湖石碑 |
 小出力の北陸電力布施川発電所 |
 布施川発電所送水管 |
 発電所付近の布施川 |
 布施川発電所放流口 |
 県道314号線布施橋 旧北陸道 |
 布施橋からあいの風とやま鉄道線 |
 布施橋から下流 |
 布施川の農道に架かる犬山橋 |
 犬山橋から上流 |
 犬山橋から下流の国道8号線橋梁 |
 河口から 青い屋根が合流地点 |
 青い屋根の石田農林漁業実習体験館 |
 石田マリーナ |
 黒瀬川河口に架かる磯橋 |
 磯橋から上流 |
 県道314号線黒瀬橋 旧北陸道 |
 左岸から布施川・片貝川合流地点 |
|
資料 施設の説明表示板、及びHP等 富山大百科事典 1994年(平成6年) 初版発行発行所 北日本新聞社 富山県歴史の道調査報告書・北陸街道1980年(昭和55年)発行 富山県教育委員会(編集)富山県郷土史会(発 行) 富山大百科事典発行の1994年(平成6年)以降の変更事項は、国土交通省のHP(河川情報)より メインページヘ |
|||